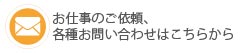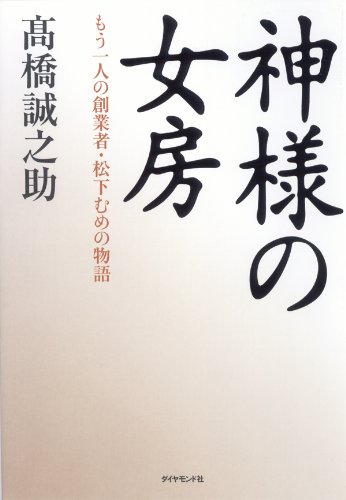高橋誠之助
ノンフィクション・小説
松下電器産業(現パナソニック)創業者-松下幸之助の松下家執事
2005年まで財団法人松下社会科学振興財団支配人
「神様」とは、そう、経営の神様を言う、、すなわち松下幸之助。
で、神様の女房だから、幸之助の奥様を指す。
著者は29歳の時、直接、幸之助より松下家の執事になることを任命され 以降20年以上に渡り松下家に関する仕事を取り仕切り、神様とその女房の臨終にも立ち会い執事を全うする。
「神様」の話は、私が小学生の頃、何度も父親から聞かされた。 その頃、自宅の近くの国道171号線沿いに「ナショナル」の大きな看板の付いた 広大な敷地を持つ会社があった。
そこの住所は社名から取った“松下町”と付けられていた。 幼心にも「これだけ大きな会社の社長さんって、どんな人だろう」 と 思ったことを 50年近く経った今でも鮮明に覚えている。
そして、同じと言うにはあまりに痴がましいが、経営者の端くれとなった今も私の中では 「神様」は生き続け、むしろ「神」を超えた存在となっている。
僅か100名程度の会社の経営ですら、これだけ苦労するのに、、である。
「神様」の本は殆ど読んだ。 またどれも何度も読み返した。
大概が、迷った時や不安になった時だ。 これが本当の「神」頼み、、というやつだと、読みながらいつもそう思う。
失礼ながら、いずれも難しいことは書いていない。 だからいつも読んだ後に安堵感が漂う、、「神」の言うことが理解出来ると。 原理原則を自身に言い聞かせて、「これで迷うことはない」と安心する。
しかし、この原理原則を継続実行することが一番難しいことを忘れて。。 あの世へ行っても、代替わりしても「神」との差は絶対埋まることは無いと こういうことだけは自信が有る自分が情けない。
さて、今回は「神様」の女房の話である。「神」にも女房が居た、、というより居たからこそ「神」が存在した。という方が正しいのだろう。
名は「むめの」という。淡路島の船乗りの次女として生まれ、後に弟の歳男は姉むめのとともに 松下電器創設の際に大きな役割を果たす。また歳男は後に生まれて来る弟、祐朗、薫と共に井植三兄弟で戦後 三洋電機を創設することになる。
比較的裕福な家で育ったむめのは、年頃となって条件の良い縁談は いくつも有った。しかし心は動かず、和歌山の田舎から出て来て大阪の電燈会社(現関西電力) に勤める。
借家住まいで無一文、その上病弱な20歳の幸之助の縁談を受けることになる 、、むめの19歳。 数ある縁談の中でも最悪の条件だったらしい。 父 清太郎の激怒ぶりがうかがえる。 挙式費用は借金、式翌日からの生活では湯呑が二人で1個、、交代で呑む。。 小学校の卒業を待たずして大阪の船場に奉公に出された幸之助にとっては 貧乏続きでさほど苦にならなかったのかもしれないが、妻むめのにとっては 大変だったことだろう。
「サラリーマン時代の給料はささやかなものであったが、食卓に肉が出ることもあった」 と後に幸之助は言っているが、当時の給料ではとても肉は食卓に出ることはなかった。むめのの内職(裁縫)で家計を助けていた秘密を幸之助が知ったのは、 実に50年も後のことであった。
ソケットの本体の練り物の調合が解らない時、他の工場のゴミ捨て場をあさり、仕損じ品を拾って来いと幸之助に言われ何日もゴミ捨て場に通ったこともあった。
ゴミ捨て場をあさることを指示するぐらいだから、営業(ソケットの売り歩き)も 勿論やっている。
創業して初めてソケットを売ったのは、むめのだったらしい。
それから幾歳月が流れ昭和10年、幸之助とむめのの個人経営であった事業を 株式会社へ変更し、それを機にむめのは一切の仕事から手を引いた。
ある時、「幸之助さんには家の中で、どう接しているのか」との周囲からの質問に 「特別なことはしないが、ただ妻は立場をわきまえなけねばならない、というのは 母からの教えで、商売して主でもあるので常に上座に迎え、何でも一番にする そのほうが主人も気持ち良く主人の役割が出来る」と答えている。
また「女房の価値は家をどれだけ取り仕切れるかということ、、家の中のことは すべて任せてこそ夫は仕事に専念出来る」とも。
個人的に一番心に残ったのは「夫婦喧嘩のあとは妻から話かけなさい」という言葉。
私も是非そう願いたい。
幸之助の死から5年、平成5年9月5日むめのは幸之助のあと追った。 享年97。
戦後一代で、従業員数38万人の巨大企業を築いた創業者を陰で支えた奥様。
礼を失するのは覚悟の上で、奥様と呼ぶより「関西の気丈なおばちゃん」 のほうが私には合っているように感じる。